今回は、当館所蔵の西山翠嶂作品《女役者》についてお話しいたします。しかしこれは皆様に作品解説をしようという記事ではございません。ただ、話を聞いていただきたい、そんな気持ちをつづってみました。長いです。

大きな紋の入った幕の前に立つ女性。着崩した格子柄の着物、余裕のあるしぐさが非常にかっこいいですね。作者自身がつけた「女役者」というタイトルが示すとおり、おそらくこの人は女性の歌舞伎役者でしょう。現在、歌舞伎を演じるのは男性のみですが、江戸時代末から大正時代の頃にかけて、女性も演じており、彼女たちは女役者と呼ばれていたのです。女団州と呼ばれた市川粂八などが最も有名でしょうか。粂八は鏑木清方によって肖像が描かれていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。
さて、彼女が誰で、この絵がいつ頃描かれたものなのかを考える前に、作者についてお話しておきたいと思います。
描いた西山翠嶂(1879-1958)は、竹内栖鳳の高弟で、娘婿でもありました。一時期、洋画家 浅井忠にも師事し、人物デッサンを学びました。風景や動植物が多い栖鳳と違い、人物画の大作を多く描き、文展や帝展などに出品しています。大正から昭和にかけて重鎮として京都の画壇を支え、自身が主宰する画塾・青甲社からは、秋野不矩・上村松篁、中村大三郎ら重要な画家を輩出しています。
そんな翠嶂ですが、落款や印章などのデータの蓄積はまだ多くはなく、文展・帝展に出品した代表作以外は年代の特定などが難しいのが現状です。この絵について調べたいと思ったとき、どうすればいいのか。まずやはり先人の研究に頼るほかありません。
幸いにも、高木多喜夫氏が研究成果として「西山翠嶂の人と画業に関する基礎調査(年譜私案)」(『京都文化博物館研究紀要「朱雀」第5集』、1992年発行)を残されています。これは、図書や雑誌ほか膨大な資料を丹念に整理されたもので、私は翠嶂を調べる上でこれをいつも頼りにしています。その中に、見逃せない箇所がありました。
明治45(1912)年6月1日、(翠嶂)33歳 女役者 現代名家風俗画集(高島屋飯田橋呉服貿易店 明治45(1912)年6月5日)に掲載。京都高島屋呉服店の新築落成記念現代名家風俗画展に出品。出典『高島屋美術部五十年史』(掲載にあたり、年号の表記など適宜変えました)
これを見つけた私はひそかに大喜びしました。当館の《女役者》は高島屋の展覧会に出たものだと確信して…。作品の出品歴がわかると何がよいかといいますと、素性がわかるということももちろん、やはり展覧会に出すということはそれだけ力を入れて描いているという想像もできるわけで、その力作に画家がどのような苦心・工夫をしたのか、調べがいも出てくるのです。また別の本を参照すると、この展覧会には栖鳳の名画《アレ夕立に》も特別に陳列されていた、という興味深い事実もわかりました。
調べで「現代名家風俗画展」の明治45年当時の図録が図書館や資料館に残されているとわかってさらに有頂天になった私は、資料を保存している図書館に突撃しました。
とある図書館へ飛び込んでカウンターで恐る恐る「すいません、『現代名家風俗画集』を見せてください」とお願いし(貴重書なので開架ではないのですね)、司書の方から本を手渡され、私はドキドキしながら年月の蓄積を感じるその本のページを丁寧にめくりました。そして…
「あれ?ない…ないよ…?」
そう、あろうことか落丁です。それも翠嶂のページだけが。なんとも驚くことではありませんか。私の落胆をお察しいただければ幸いです。
そして次の機会を求めて待つこと数ヶ月。オープンしたての京都府立京都学・歴彩館にて、とうとう図録を手にすることができました。そして、確認することができたのです。
当館の《女役者》は高島屋呉服店現代名家風俗画展出品の《女役者》ではないということを…。
森下麻衣子






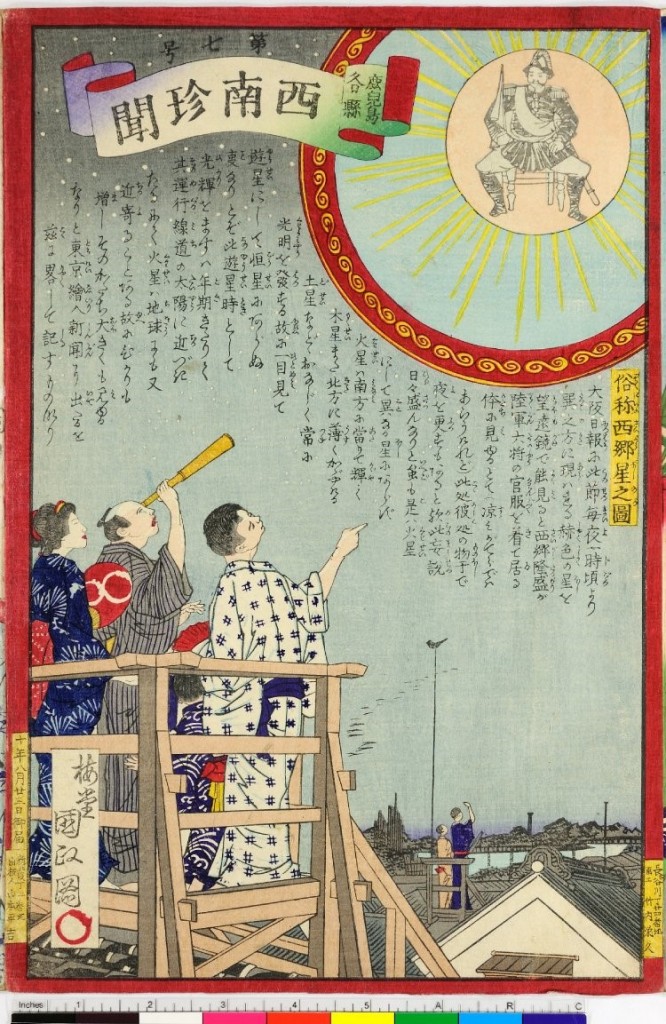





-1-300x200.jpg)
-2-300x200.jpg)
-3-300x200.jpg)
-1-300x200.jpg)
-2-300x200.jpg)
-5-300x200.jpg)
-6-300x200.jpg)
-7-300x200.jpg)
-6-300x200.jpg)
-8-300x200.jpg)
-7-300x200.jpg)
-16-300x200.jpg)
-15-300x200.jpg)
-14-300x200.jpg)
の木の花-2-300x200.jpg)
の木の花-1-300x200.jpg)
の木の花-3-300x200.jpg)